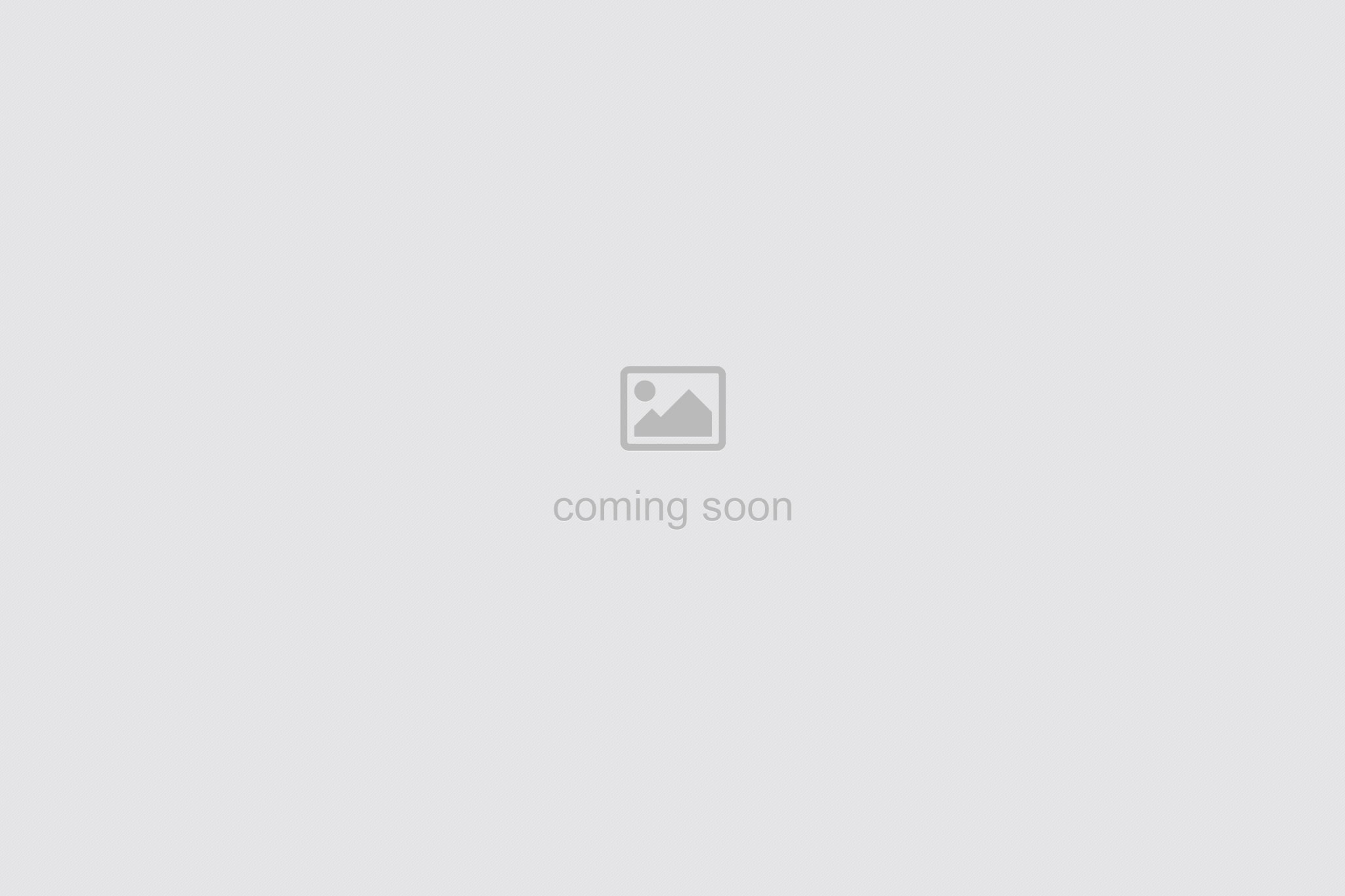位置
地形・地質
概況
中古成層が広く分布する丹波帯に属し、主に風化の進んだ花崗岩や古琵琶湖層群から構成されています。このため、「近江富士」で名高い三上山(432m)の西麓を境に、野洲川上中流部では浸食により河谷地形が形成され、下流部では激しく生産される土砂の堆積により広大な扇状地、日本最大の湖成三角州が形成されています。
野洲川
野洲川は、鈴鹿山脈の主峰、御在所岳(標高1,212m)を水源とし、流域面積387㎢、全長65㎞の県下最大の河川であり、田村川、杣川等の支流と合流し、琵琶湖に注いでいます。
昔は4本の大きな流れがあり、それぞれから分かれた流れが低地に沿って放射状に、ある時は網目状に琵琶湖に注いでいたため、河口部は多くの洲があったことから八洲川と呼ばれ、後に野洲川となったともいわれております。
また、野洲川は利根川の「坂東太郎」にならって「近江太郎」とよばれ恵みをもたらす一方で、「暴れ川」としてたびたび流域に洪水をもたらしてきました。また、その流域は保水力に乏しく、かつ河床は急勾配であるため流水の持続性が低いため、野洲川ダムができるまでは頻繁に用水不足が生じ水争いが絶えませんでした。
歴史
古墳群や銅鐸
明治14年と昭和37年に、野洲市の大岩山から、あわせて24個の銅鐸が発見されました。銅鐸は、二千年ほど前のものだということが分かっており、稲作の豊作を祈願する祭りで使用され、後になって観賞用の銅鐸に変化していったといわれています。発見されたものの中には、134.7㎝で日本最大のものも含まれていました。
野洲川流域には数多くの古墳が発見されています。同じ大岩山の近くから、4~6世紀頃のものと思われる17基の古墳も見つかっています。その内8つは国の史跡に指定されています。古墳築造技術の高さは、千五百年ほど前、朝鮮半島や大陸から近江の地に移り住んだといわれている渡来人とも関係があり、渡来人は、この地にレベルの高い土木技術、農具、漢字、宗教などを伝えたといわれています。
幻に終わった紫香楽の宮
740年、聖武天皇は都を山城国(京都)の恭仁京に遷都を計画しました。天皇は、同時に別荘にあたる離宮(紫香楽の宮)の築造命令を出しており、その地として現在の甲賀市信楽町が選ばれました。
聖武天皇は、仏教振興に力をそそいだ人物として知られていますが、大仏建立が奈良の東大寺に決まる前に、離宮築造予定地のすぐ側、甲賀の地に大仏を造るよう詔をだしていました。大仏建立は、その地を仏都、すなわち仏教文化の中心地にするということを意味しています。古くから文化的に発展してきた野洲川流域(甲賀市)ゆえに、聖武天皇の目にとまったのかも知れません。
しかし、当時影響力をもっていた藤原氏の発言により、恭仁京の築造は中止されました。また、地震や山火事などの影響によって、大仏建立も中止となりました。かくして、仏教文化の中心地「紫香楽の宮」の築造は幻に終わりました。
歴史に登場する野洲川流域
672年、大海人皇子と大友皇子の皇位をめぐる争い「壬申の乱」が勃発しました。そのことが記された「日本書記」には、野洲川流域の地名が登場します。
不破の関(関ヶ原)より大友皇子のいる近江宮(大津宮ともいう)を目指し出陣した大海人皇子の軍隊は、途中、東山道(中山道の古称、現在の国道8号線)入り湖東を南下しました。大友皇子率いる朝廷軍は、逆に不破の関へと向かっていました。野洲川の流域に入って初めに両軍がぶつかるのが、安河(やすのかわ:現野洲川)であります。安河の戦いで勝利した大海人皇子は、続いて栗田(現栗東市)で大友軍を破り、瀬田に至ったとされています。
平安時代末期、平家は壇ノ浦の合戦(1185年)に敗れます。平家の大将である平宗盛とその子どもは捕えられ、鎌倉へと連行されました。しかし、源頼朝から平家の鎌倉入りを禁止するという命令が出たため、京都へと引き返すことになりました。そして、宗盛親子は、京都を目前にした現在の野洲市大篠原で、同行していた源義経の手によって処刑されました。その場所には、「平宗盛卿終焉之地」と刻まれた石碑が建てられています。
この地は、古くから東日本と西日本を結ぶ交通の要衝であり、軍事的にも重要な位置を占めていました。
中世の動乱
1221年、朝廷と鎌倉幕府との間で承久の乱が起こった。朝廷の倒幕の目論見は破れ、幕府軍の勝利に終わりました。幕府は近江の地のほか、朝廷の息がかかった地域に地頭を配置します。承久の乱で功績をあげた佐々木信綱は、幕府より、栗太郡の地頭職を任命されました。しかし、この地は中世より延暦寺系の独自の権力基盤が確立していたため、佐々木氏の地頭職は実現できなかったといいます。
その後も、この地は地頭(もしくは守護)による一体的な支配がなされぬまま、延暦寺系の荘園によって、戦国時代まで独自の統治が行われていくことになります。
応仁の乱から戦国時代へと突入すると、この地はまたしても戦乱の渦に巻き込まれていくことになりました。現在の甲賀市や守山市は、このときの争いで焼け野原になってしまったと記録されています。
分散領有の歴史
歴史的にこの地は、分散領有されてきたことが分かります。中世は佐々木氏の支配下にあったものの、上流部は六角氏系の甲賀53家、下流平野は三上7党と呼ばれた土豪集団が支配していました。
豊臣秀吉が天下を統一すると、この地は豊臣家の直轄地になったが、江戸時代になると、再びその領有は分散された。主だった平野部は彦根領、膳所藩、水口藩、遠藤氏などの領有が占め、他は10数に及ぶ他国大名、天領、100を超える旗本領などが錯綜して複雑多岐な領有関係をなしていました。例えば、野洲郡小田村の村高760石は12の領主によって分領されていたといいます。
したがって、この地には藩や篤農家による大規模な水利開発や新田開発は見られません。野洲川の水の少なさに加え、この複雑な分散領有の歴史が水争いの苛烈さをましたといえます。